【日本学生支援機構の制度を徹底解説】これを読めば日本学生支援機構の全ての奨学金がわかる!

国内で最も多くの大学生が申し込みをしている日本学生支援機構(JASSO)の奨学金ですが、その奨学金には多くの種類があり、どれが自分に合っている奨学金なのかを理解するには時間がかかってしまいます。
そこで本記事では日本学生支援機構の奨学金を全て解説するとともに、どの制度が自分に合っているかまでわかるようにしています。または先に理解が進むように日本学生支援機構の奨学金を図でまとめましたので、まずはこちらをご覧ください。

日本学生支援機構の奨学金の奨学金制度は大きく分けると「給付型」と「貸与型」に分けることができます。「給付型」は返済の必要がない奨学金となっています。
「貸与型」の奨学金は返済の必要がある奨学金となっていますが、その中でも「第一種奨学金」というのは無利子の奨学金となっており、借りた分だけの返済で済むので卒業後の負担は軽いです。「第二種奨学金」というのは利子が上限3%と他の民間のローンよりは負担が軽いですが、借りた金額以上の返済をしなければならないためしっかりと返済計画を立てる必要があります。
最後に「入学時特別増額貸与奨学金」ですが、これは年間を通して借りる奨学金ではなく、入学時のお金がかかるタイミングで借りられる奨学金です、こちらも利子ありの奨学金となっているため便利な制度ですが、しっかりと返済計画を立てて活用しておきましょう。
また、奨学金の申し込みには3種類あり、進学前に申し込みをする「予約採用」と、進学後に申し込みをする「在学採用」と、突発的に奨学金が必要になった人が申し込む「緊急採用」があります。
それぞれの奨学金を解説する際に、申し込み形態別の採用基準も説明しますので、自分がどの申し込み方法に当たるのかを確認しながら読みましょう。
また、ガクシーでは充実した奨学金検索機能や、アカウント登録後のリマインド機能から、あなたに合った奨学金を見つけ忘れずに申し込みをするところまでサポートしています。
申し込みの期日のリマインドや、お得な奨学金情報は会員登録をすると受け取ることができます。 是非登録してお得な奨学金情報を漏らさずチェックしてください。
▼会員登録する
https://gaxi.jp/auth/login
では、それぞれの奨学金を見ていきましょう。
目次
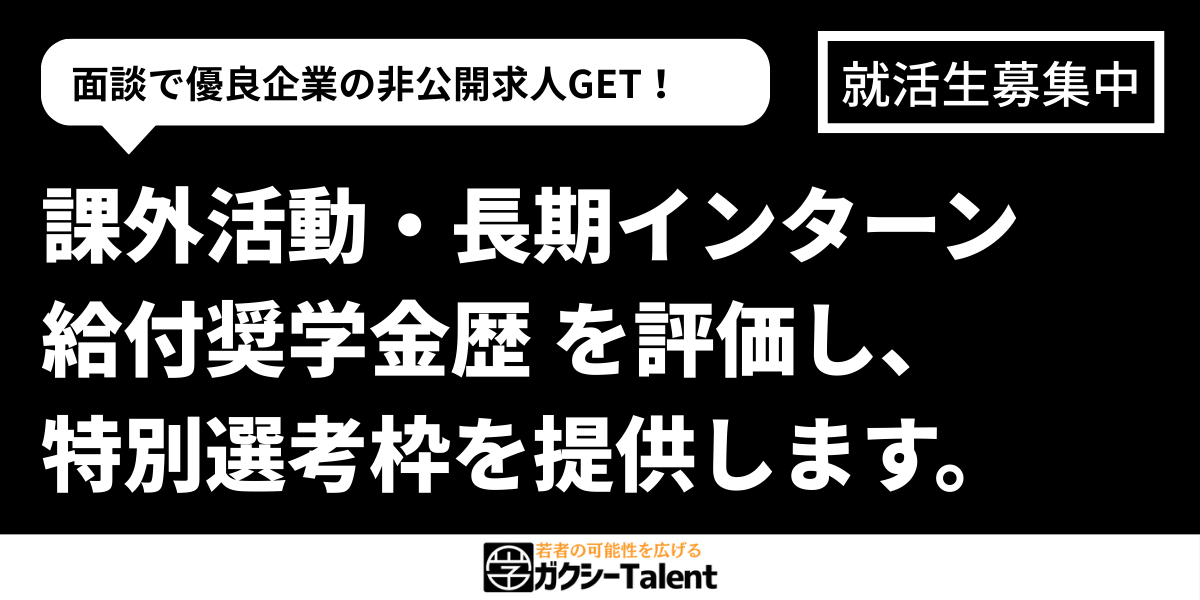
【就活生必見】ガクシーが独自評価で非公開求人をご提供。
ガクシーTalentは、課外活動・長期インターン・給付奨学金の選考歴を独自評価し、優良企業の非公開求人や特別選考枠を提供する就活サービスです
詳細を見る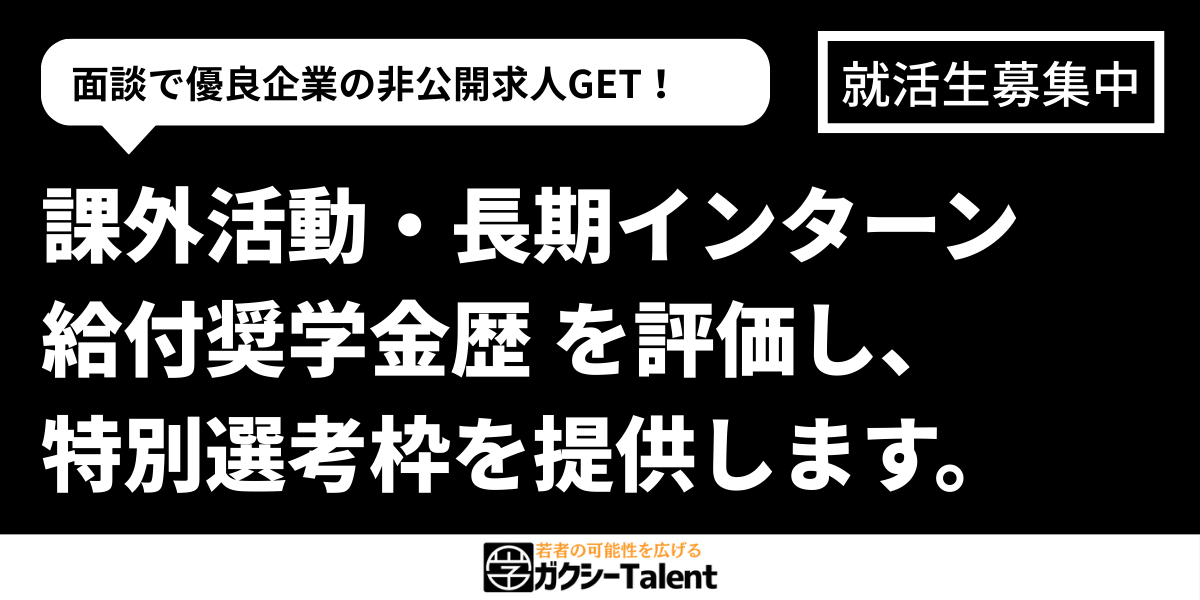
【就活生必見】ガクシーが独自評価で非公開求人をご提供。
ガクシーTalentは、課外活動・長期インターン・給付奨学金の選考歴を独自評価し、優良企業の非公開求人や特別選考枠を提供する就活サービスです
詳細を見る給付型奨学金(返済不要)
日本学生支援機構の給付型奨学金制度は令和5年に
大学(学部・大学院)が252,069名
短期大学・高等専門学校が 16,366名
専修学校(専門課程)が73,378名
合計341,813名を奨学生として採用している、日本最大の給付型奨学金となっています。
給付型の奨学金というのは言い換えると返済不要の奨学金ということで、もし申し込み基準を満たしているとしたら必ず申し込んでおいたほうがいい制度と言えます。また本制度は2025年に制度がリニューアルされており、「給付型奨学金の増額」「入学金や授業料の減額・免除」「対象学生の増枠」「多子世帯・理工農系への支援拡充」などが変更点となっています。ただでさえメリットが大きい制度にさらにメリットが増えました。ではここから「どんな人が申し込み資格があるのか?」「どのくらいの金額が支給されるのか?」を順番に見ていきましょう。
対象となる学生
給付型奨学金の対象となる学生は「予約採用」か「在学採用」かによって違います。それぞれを見ていきましょう。
予約採用の場合
予約採用は進学前に奨学金に申し込みをする方法です。下記にわかりやすく図を作成しましたのでご覧ください。
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 家計基準 | 住民税非課税世帯に加え、準ずる世帯(非課税世帯の2/3または1/3の額を支給) |
| 学力基準 | 高等学校等における全履修科目の評定平均値が、5段階評価で3.5以上であること |
| 将来、社会で自立し、及び活躍する目標をもって、進学しようとする大学等における学修意欲を有すること |
家計基準は4つの種類に分類されます。
| 支援区分 | 収入基準(※1) |
|---|---|
| 第Ⅰ区分 | あなたと生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること(※2) 具体的には、あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円未満であること |
| 第Ⅱ区分 | あなたと生計維持者の支給額算定基準額(※3)の合計が100円以上25,600円未満であること |
| 第Ⅲ区分 | あなたと生計維持者の支給額算定基準額(※3)の合計が25,600円以上51,300円未満であること |
| 第Ⅳ区分 | あなたと生計維持者の支給額算定基準額(※3)の合計が51,300円以上154,500円未満であること |
以上の4つのどれかに該当すれば家計基準は満たしています。注意点としては、どの区分に入るかにより支給される金額が変わってくる点です。支給金額に関しては後ほど解説します。
次に学力基準ですが「高等学校等における全履修科目の評定平均値が、5段階評価で3.5以上であること」か「将来、社会で自立し、及び活躍する目標をもって、進学しようとする大学等における学修意欲を有すること」のいずれかを満たしていればよく、成績が5段階評価で3.5以上なくても、申し込みの際に作成するレポートで挽回できる可能性があります。
詳しい申し込み書の書き方はこちら「【奨学金申し込み書類の書き方解説】用意するものや申請理由の書く時に役立つ7つの例文を紹介!」で紹介していますので、参考にしてみてください。
在学採用の場合
在学採用は進学後に奨学金に申し込みをする方法です。下記にわかりやすく図を作成しましたのでご覧ください。
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 家計基準 | 住民税非課税世帯に加え、 準ずる世帯(非課税世帯の2/3または1/3の額を支給) |
| 学力基準 | 【1年次】 ・高等学校等における全履修科目の評定平均値が、5段階評価で3.5以上であること ・将来、社会で自立し、及び活躍する目標をもって、進学しようとする大学等における学修意欲を有すること |
| 【2年以上次】 ・GPA(平均成績)等が在学する学部等における上位2分の1の範囲に属すること ・修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること |
家計基準に関しては予約採用と大きな変わりはございません。特徴的なのは学力基準です。
在学採用での学力基準は「1年次」と「2年以上次」によって分かれる点が特徴的です。1年次での学力基準は予約型と条件に変わりはありませんが、2年次以上になると大学での成績が加味されます。よって1年次に申し込んでおけば審査を通過できたが、2年次以上だと通過できなくなってしまったというケースもあるので学年が変わる際には注意が必要です。
支給される金額
給付型奨学金で学校に通う時には「世帯年収の区分」と「進学先が国立なのか私立なのか」と「自宅通学か自宅外通学か」などの条件よって支給される金額が変わってきます。各条件の支給金額を図でまとめましたのでご確認ください。
国公立の場合
| 区分 | 自宅通学 | 自宅外通学 |
|---|---|---|
| 大学・短期大学・専修学校(専門課程) | ||
| 第Ⅰ区分 | 29,200円(33,300円) | 66,700円 |
| 第Ⅱ区分 | 19,500円(22,200円) | 44,500円 |
| 第Ⅲ区分 | 9,800円(11,100円) | 22,300円 |
| 第Ⅳ区分(多子世帯に限る) | 7,300円(8,400円) | 16,700円 |
| 高等専門学校(第4学年以上) | ||
| 第Ⅰ区分 | 17,500円(25,800円) | 34,200円 |
| 第Ⅱ区分 | 11,700円(17,200円) | 22,800円 |
| 第Ⅲ区分 | 5,900円(8,600円) | 11,400円 |
| 第Ⅳ区分(多子世帯に限る) | 4,400円(6,500円) | 8,600円 |
私立の場合
| 区分 | 自宅通学 | 自宅外通学 |
|---|---|---|
| 大学・短期大学・専修学校(専門課程) | ||
| 第Ⅰ区分 | 38,300円(42,500円) | 75,800円 |
| 第Ⅱ区分 | 25,600円(28,400円) | 50,600円 |
| 第Ⅲ区分 | 12,800円(14,200円) | 25,300円 |
| 第Ⅳ区分(多子世帯に限る) | 9,600円(10,700円) | 19,000円 |
| 高等専門学校(第4学年以上) | ||
| 第Ⅰ区分 | 26,700円(35,000円) | 43,300円 |
| 第Ⅱ区分 | 17,800円(23,400円) | 28,900円 |
| 第Ⅲ区分 | 8,900円(11,700円) | 14,500円 |
| 第Ⅳ区分(多子世帯に限る) | 6,700円(8,800円) | 10,900円 |
また2025年の給付型奨学金制度のリニューアルに伴い、奨学金とは別に入学金や授業料も免除されます。支給金額は各区分やお子さまの数によって変わります。下記に表でまとめてありますので参考にしてみてください。
| 所得の区分 (年収目安) | 1子・2子世帯 (資産要件:授業料等減免・給付奨学金とも5,000万円未満) | 多子世帯 (資産要件:授業料等減免3億円未満、給付奨学金5,000万円未満) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支援区分 (呼称) | 授業料等減免 支援額 | 給付奨学金 支給額 | 第一種奨学金 からの控除額 (併給調整) | 支援区分 (呼称) | 授業料等減免 支援額 | 給付奨学金 支給額 | 第一種奨学金 からの控除額 (併給調整) | |
| ~270万円 | 第I区分 | 満額 | 満額 | 減免満額 + 給付満額 | 第I区分 (多子世帯) | 満額 | 満額 | 減免満額 + 給付満額 |
| ~300万円 | 第II区分 | 2/3 | 2/3 | 減免2/3 + 給付2/3 | 第II区分 (多子世帯) | 満額 | 2/3 | 減免満額 + 給付2/3 |
| ~380万円 | 第III区分 | 1/3 | 1/3 | 減免1/3 + 給付1/3 | 第III区分 (多子世帯) | 満額 | 1/3 | 減免満額 + 給付1/3 |
| ~600万円 (理工農系) | 第IV区分 (理工農系) | 1/4 (大学(除通信)・高専は1/3) | 無し | 減免1/4 (大学(除通信)・高専は減免1/3) | 第IV区分 (多子世帯) | 満額 | 1/4 | 減免満額 + 給付1/4 |
| 上記以外 | - | 不採用/停止 | 不採用/停止 | 控除(調整)なし (希望額を貸与) | - | 不採用/停止 | 不採用/停止 | 控除(調整)なし (希望額を貸与) |
| 600万円~ | - | 不採用/停止 | 不採用/停止 | 控除(調整)なし (希望額を貸与) | 多子世帯 | 満額 | 無し | 減免満額 |
日本学生支援機構の給付型奨学金については【奨学金の新制度】2020年からリニューアルされた日本学生支援機構の「給付型奨学金」とは?で詳しく解説をしているので、参考にしてください。
貸与型奨学金|第一種奨学金(返済必要)
貸与型奨学金の中で第一種奨学金は返済の必要はあるが利子のない奨学金になっています。借りた金額と同じ金額を卒業後に返していくので、奨学生の負担は軽くおすすめの奨学金になっています。では、それぞれ対象となる学生と借りられる金額を見ていきましょう。
対象となる学生
第一種奨学金の対象となる学生は「予約採用」か「在学採用」かによって違います。それぞれを見ていきましょう。
予約採用の場合
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 家計基準 | 世帯人数と収入による(下記貸与型奨学金家計基準参照) |
| 学力基準※いずれかを満たしていること |
(1)高等学校等における申込時までの全履修科目の評定平均値が、5段階評価で3.5以上であること。 ただし、上記の基準を満たさない場合であっても、生計維持者(原則父母。父母がいない場合は代わって生計を維持している人)の住民税が非課税(市町村民税所得割額が0円)である者、生活保護受給世帯である者または社会的養護を必要とする者(児童養護施設等入所者、里親による養育を受けている者等)であって、次のアまたはイのいずれかに該当する者は、第一種奨学金の学力基準を満たす者として取り扱うことができます。 ア.特定の分野において、特に優れた資質能力を有し、特に優れた学習成績を修める見込みがあること。 イ.学修に意欲があり、特に優れた学習成績を修める見込みがあること。 (2)高等学校卒業程度認定試験合格者であること。 |
■各貸与型奨学金家計基準
| 希望する奨学金 | 家計基準(※1) |
|---|---|
| 第一種・第二種併用貸与 | 生計維持者の貸与額算定基準額(※2)が164,600円以下であること |
| 第一種奨学金 | 生計維持者の貸与額算定基準額が189,400円以下であること |
| 第二種奨学金 | 生計維持者の貸与額算定基準額が381,500円以下であること |
在学採用の場合
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 家計基準(平成30年度以降) | 世帯人数と収入による(上記貸与型奨学金家計基準参照) |
| 学力基準(2021年入学の場合)※いずれかを満たしていること | (1)高等学校または専修学校高等課程最終2か年の成績の平均が3.5(専修学校(専門課程)の場合は3.2)以上であること |
| (2)高等学校卒業程度認定試験に合格者であること | |
| (3)生計維持者(原則父母。父母がいない場合は代わって生計を維持している人)の住民税が非課税(市町村民税所得割額が0円)である者、生活保護受給世帯である者又は社会的養護を必要とする者(児童養護施設等入所者、里親による養育を受けている者等)であって、以下のいずれかに該当すること |
借りられる金額
第一種奨学金も給付型と同様に「進学先が国公立か私立なのか」と「自宅通学か自宅外通学なのか」「給付型奨学金の併用ありかなしか」によって分かれます。そして貸与の額に関しては該当の枠の中から自分で選択が可能となります。以下に貸与額に関してまとめているので、よろしければ参考にしてみてください。
また給付型奨学金と併せて第一種奨学金の貸与を受ける場合、給付奨学金の支援区分等に応じて、第一種奨学金の貸与月額が調整されます(多くの場合は減額となり、0円となる場合もあります)。また多子世帯支援拡充により、多子世帯の方は給付型奨学金と授業料免除の支援金額が変わるのでご注意ください。
■第一種奨学金の貸与月額(給付型奨学金併用あり)
| 区分 | 第1区分 | 第2区分 | 第3区分 | 第4区分(多子世帯) | 第4区分(理工農系) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国公立 自宅 | 0円 (0円) | 0円 (0円) | 20,300円 (25,000円) | 26,500円 (20,000円、31,400円) | 併給調整なし |
| 国公立 自宅外 | 0円 | 0円 | 13,800円 | 23,100円 | 併給調整なし |
| 私立 自宅 | 0円 (0円) | 0円 (0円) | 21,700円 (20,000円、30,300円) | 29,800円 (20,000円、38,700円) | 20,000円、34,500円 (20,000円、30,000円、44,500円) |
| 私立 自宅外 | 0円 | 0円 | 19,200円 | 20,000円、30,400円 | 20,000円、30,000円、44,500円 |
■第一種奨学金の貸与月額(給付型奨学金併用なし)
| 区分 | 自宅通学 | 自宅外通学 |
|---|---|---|
| 国公立大学 | 20,000円、30,000円、45,000円 | 20,000円、30,000円、40,000円、51,000円 |
| 私立大学 | 20,000円、30,000円、40,000円、54,000円 | 20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、64,000円 |
第一種奨学金に関しては【第一種奨学金】無利子の奨学金借りるには?申し込み方法・採用基準を徹底解説!で詳しく解説していますので、参考にしてください。
貸与型奨学金|第二種奨学金(返済必要)
第二種奨学金は、返済が必要かつ利子がつくタイプの奨学金のことです。卒業後に年利3%が上限として利息がつきます。第一種程ハードルは高くないものの、成績が標準以上であったり、特定の分野での素質が認められていたり、学修意欲がある且つ修了見込みがあったりする必要があります。
対象となる学生
第二種奨学金の対象となる学生の家庭基準と学力基準は以下の通りになります。給付型や第一種奨学金と比べるとかなり枠が広がっています。家計基準に関しては日本の40代と50代の平均世帯年収が700万円前後であるとこから、かなり多くの世帯が該当すると言えるでしょう。
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 家計基準 | 世帯人数と収入による(下記貸与型奨学金家計基準参照) |
| 学力基準※いずれかを満たしていること |
・高等学校または専修学校(高等課程)における学業成績が平均水準以上と認められる者 ・特定の分野において特に優れた資質能力を有すると認められる者 ・大学における学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見込みがあると認められる者 ・高等学校卒業程度認定試験に合格した人または科目合格者で機構の定める基準に該当する人 |
■各貸与型奨学金家計基準
| 希望する奨学金 | 家計基準(※1) |
|---|---|
| 第一種・第二種併用貸与 | 生計維持者の貸与額算定基準額(※2)が164,600円以下であること |
| 第一種奨学金 | 生計維持者の貸与額算定基準額が189,400円以下であること |
| 第二種奨学金 | 生計維持者の貸与額算定基準額が381,500円以下であること |
借りられる金額
第二種奨学金で借りられる金額は20,000~120,000円となっており、10,000円刻みで貸与したい金額を選ぶことができます。また私立大学の医・歯学の課程の場合はさらに上限が40,000円、私立大学の薬・獣医学の課程の場合は20,000円さらに上限が引き上がるので、自身が進学する学部がどこに該当するかを確認しておきましょう。
第二種奨学金に関しては【第二種奨学金】有利子の奨学金を借りるには?申し込み方法・採用基準・第一種との違いも解説!で詳しく解説をしているので、参考にしてください。
入学時特別増額貸与奨学金(返済必要)
対象となる学生
対象は4人世帯の給与所得が400万円以下、または国の教育ローンを申し込んだが落ちてしまった方が対象になります。
借りられる金額
貸与金額は10万円~50万円を10万円刻みで申請することができます。また、入学時特別増額貸与奨学金は予約採用で採用されても、入学時に辞退することができるので、他の奨学金が採用されなかった時のための保険としてとりあえず申し込んでおくことをおすすめします。
入学時と名前についている奨学金ですが、他の貸与型の奨学金と同じく、第一回目の振り込み日(4月21日になることが多い)となるため、入学前に借りることはできないので注意が必要です。
併用条件
日本学生支援機構の各奨学金の併用条件をまとめましたのでまずは下記の表をご覧ください。
| 所得の区分 (年収目安) | 1子・2子世帯 (資産要件:授業料等減免・給付奨学金とも5,000万円未満) | 多子世帯 (資産要件:授業料等減免3億円未満、給付奨学金5,000万円未満) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支援区分 (呼称) | 授業料等減免 支援額 | 給付奨学金 支給額 | 第一種奨学金 からの控除額 (併給調整) | 支援区分 (呼称) | 授業料等減免 支援額 | 給付奨学金 支給額 | 第一種奨学金 からの控除額 (併給調整) | |
| ~270万円 | 第I区分 | 満額 | 満額 | 減免満額 + 給付満額 | 第I区分 (多子世帯) | 満額 | 満額 | 減免満額 + 給付満額 |
| ~300万円 | 第II区分 | 2/3 | 2/3 | 減免2/3 + 給付2/3 | 第II区分 (多子世帯) | 満額 | 2/3 | 減免満額 + 給付2/3 |
| ~380万円 | 第III区分 | 1/3 | 1/3 | 減免1/3 + 給付1/3 | 第III区分 (多子世帯) | 満額 | 1/3 | 減免満額 + 給付1/3 |
| ~600万円 (理工農系) | 第IV区分 (理工農系) | 1/4 (大学(除通信)・高専は1/3) | 無し | 減免1/4 (大学(除通信)・高専は減免1/3) | 第IV区分 (多子世帯) | 満額 | 1/4 | 減免満額 + 給付1/4 |
| 上記以外 | - | 不採用/停止 | 不採用/停止 | 控除(調整)なし (希望額を貸与) | - | 不採用/停止 | 不採用/停止 | 控除(調整)なし (希望額を貸与) |
| 600万円~ | - | 不採用/停止 | 不採用/停止 | 控除(調整)なし (希望額を貸与) | 多子世帯 | 満額 | 無し | 減免満額 |
基本的に併用は可能な日本学生支援機構の奨学金ですが、給付型と第一種奨学金の併用は「給付型奨学金と第一種奨学金の合計が月額54,000円以内」になることが条件があるので注意が必要です。下記にわかりやすいように図にまとめましたので参考にしてください。

出典: 日本学生支援機構のリーフレット
また、給付型と第一種奨学金を合わせても足りない場合はさらに第二種奨学金も借りるなどとにかくなるべく給付型と第一種を使えるように組み合わせることが良いと思います。
まとめ
以上が日本学生支援機構の奨学金の解説でした。基準を満たしているのであれば給付型と第一種には絶対に申し込んでおいたほうが得でしょう。どうしても利子を払うのが嫌だ、本当に家計がギリギリだという方は日本学生支援機構の奨学金以外に民間の奨学金も組み合わせて利用すべきでしょう。
また、本記事では紹介しきれなかった返済方法に関しては奨学金の返済の仕方を解説|返済方法にはどんな種類があるの?で解説をしています。
ガクシーでは充実した奨学金検索機能や、アカウント登録後のリマインド機能から、あなたに合った奨学金を見つけ忘れずに申し込みをするところまでサポートしています。
申し込みの期日のリマインドや、お得な奨学金情報は会員登録をすると受け取ることができます。 是非登録してお得な奨学金情報を漏らさずチェックしてください。
▼会員登録する
https://gaxi.jp/auth/login
会員登録でもっと奨学金を活用しよう
ガクシーに会員登録すると、あなたにピッタリの奨学金情報や便利な機能が使えるようになります。無料で簡単に登録できます!
会員登録のメリット
- 奨学金リマインダーで、オトクな奨学金を見逃さない
- ガクシー上で奨学金に申込みができる
- プロフィール登録で、奨学金に申込み時の入力が簡単になる
- プロフィールに応じたオススメ奨学金情報がメールで届く
