【第一種奨学金】無利子の奨学金を借りるには?申し込み方法・採用基準を徹底解説!

これから進学するにあたって奨学金制度を利用しようと考えている方もいらっしゃると思います。奨学金制度とはもともと進学したいが経済的な理由から諦めることがないようにと設けられました。日本学生支援機構の令和2年度の調査によると大学(昼間部)で約49.6%の人が奨学金を利用しているとされています。
今回は、大学生の約3人に1人が利用している日本学生支援機構(JASSO)の貸与奨学金の中でも、利子がかからない「第一種奨学金」について解説します。
また、ガクシーでは充実した奨学金検索機能や、アカウント登録後のリマインド機能から、あなたに合った奨学金を見つけ忘れずに申し込みをするところまでサポートしています。
申し込みの期日のリマインドや、お得な奨学金情報は会員登録をすると受け取ることができます。 是非登録してお得な奨学金情報を漏らさずチェックしてください。
▼会員登録する
https://gaxi.jp/auth/login
目次
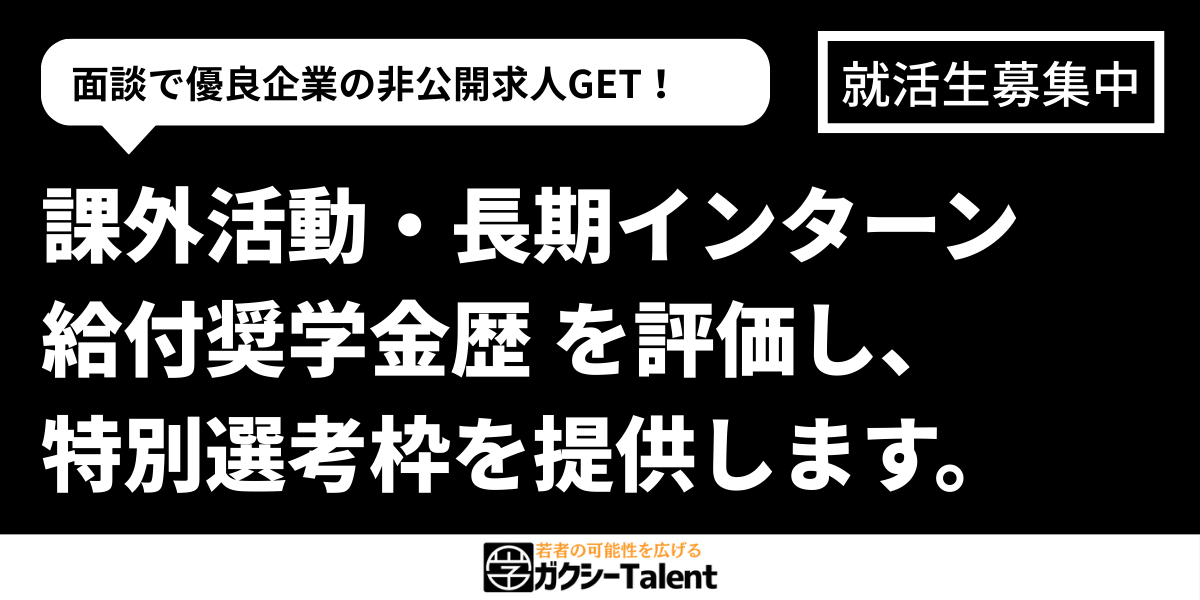
【就活生必見】ガクシーが独自評価で非公開求人をご提供。
ガクシーTalentは、課外活動・長期インターン・給付奨学金の選考歴を独自評価し、優良企業の非公開求人や特別選考枠を提供する就活サービスです
詳細を見る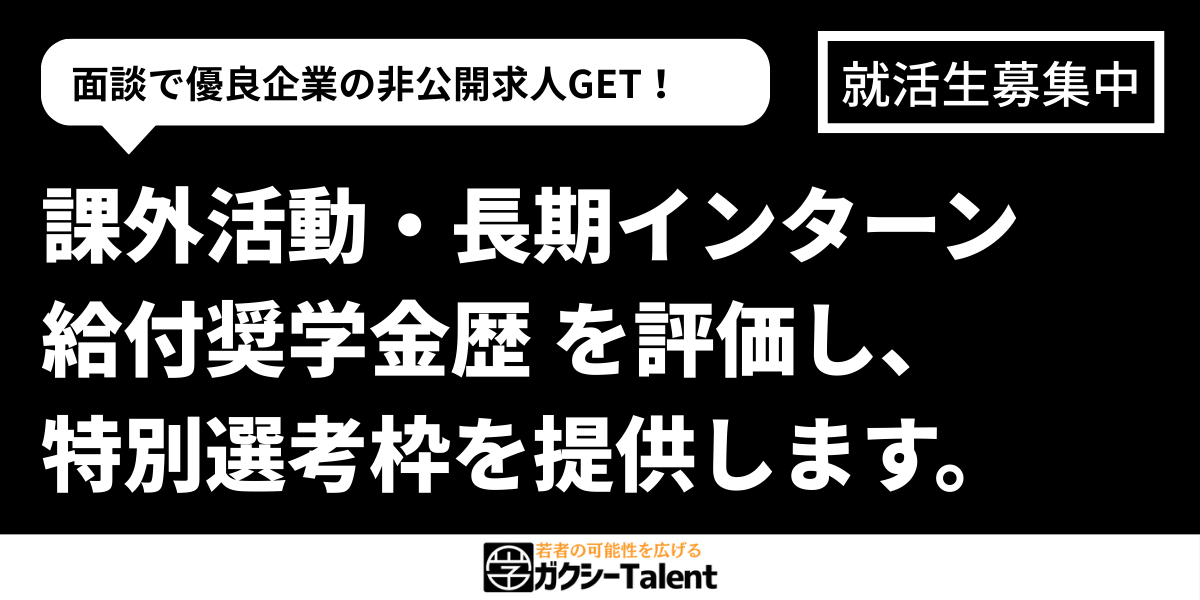
【就活生必見】ガクシーが独自評価で非公開求人をご提供。
ガクシーTalentは、課外活動・長期インターン・給付奨学金の選考歴を独自評価し、優良企業の非公開求人や特別選考枠を提供する就活サービスです
詳細を見る日本学生支援機構(JASSO)とは
現在各大学や地方自治体、民間企業など奨学金制度を実施している団体は多くありますが、その中で最も多くの学生が利用しているのが日本学生支援機構の奨学金です。日本学生支援機構は2004年4月1日に設立された独立行政法人です。
国の奨学金事業を運営していた日本育英会から奨学金事業や国の留学生に対する奨学金の給付事業、学生生活調査などの事業を引き継ぎました。奨学金事業は憲法、教育基本法に定める「教育の機会均等」の理念のもと、経済的理由で修学が困難な優れた学生等に学資の貸与及び給付を行っています。
第一種奨学金
 第一種奨学金は返還が必要な無利子の貸与型奨学金で、「給付型奨学金併用あり」と「給付型奨学金併用なし」の2つに分かれます。特徴としては、優れた学生で経済的理由により著しく修学が困難な者に貸与しています。そのため、有利子の第二種奨学金に比べて選考条件(学力・家計)が厳しくなっています。
返還は第二種奨学金同様、貸与終了(卒業など)後7か月目から始まります。
また給付型奨学金併用している方は高等教育の修学支援新制度が適用されているので、区分に応じて授業料の免除・減額が受けられます。
第一種奨学金は返還が必要な無利子の貸与型奨学金で、「給付型奨学金併用あり」と「給付型奨学金併用なし」の2つに分かれます。特徴としては、優れた学生で経済的理由により著しく修学が困難な者に貸与しています。そのため、有利子の第二種奨学金に比べて選考条件(学力・家計)が厳しくなっています。
返還は第二種奨学金同様、貸与終了(卒業など)後7か月目から始まります。
また給付型奨学金併用している方は高等教育の修学支援新制度が適用されているので、区分に応じて授業料の免除・減額が受けられます。
第一種奨学金の貸与月額(給付型奨学金併用あり)
給付型奨学金と併せて第一種奨学金の貸与を受ける場合、給付奨学金の支援区分等に応じて、第一種奨学金の貸与月額が調整されます(多くの場合は減額となり、0円となる場合もあります)。また多子世帯支援拡充により、多子世帯の方は給付型奨学金と授業料免除の支援金額が変わるのでご注意ください。
■第一種奨学金の貸与月額(給付型奨学金併用あり)
| 区分 | 第1区分 | 第2区分 | 第3区分 | 第4区分(多子世帯) | 第4区分(理工農系) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国公立 自宅 | 0円 (0円) | 0円 (0円) | 20,300円 (25,000円) | 26,500円 (20,000円、31,400円) | 併給調整なし |
| 国公立 自宅外 | 0円 | 0円 | 13,800円 | 23,100円 | 併給調整なし |
| 私立 自宅 | 0円 (0円) | 0円 (0円) | 21,700円 (20,000円、30,300円) | 29,800円 (20,000円、38,700円) | 20,000円、34,500円 (20,000円、30,000円、44,500円) |
| 私立 自宅外 | 0円 | 0円 | 19,200円 | 20,000円、30,400円 | 20,000円、30,000円、44,500円 |
第一種奨学金の貸与月額(給付型奨学金併用なし)
貸与月額は学校の設置者(国公立・私立)及び通学形態(自宅通学・自宅外通学)等により決まります。たとえば、私立大学に自宅から通学する場合、5.4万円、4万円、3万円、2万円の中から選択します。
■第一種奨学金の貸与月額(給付型奨学金併用なし)
| 区分 | 自宅通学 | 自宅外通学 |
|---|---|---|
| 国公立大学 | 20,000円、30,000円、45,000円 | 20,000円、30,000円、40,000円、51,000円 |
| 私立大学 | 20,000円、30,000円、40,000円、54,000円 | 20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、64,000円 |
*第一種奨学金「最高月額」の利用には、最も厳しい併用貸与(第一種と第二種の両方の貸与)の家計基準を満たしている必要があります。
出典:日本学生支援機構の貸与奨学金案内
第一種奨学金の選考基準
第一種奨学金の選考基準には、家計基準と学力基準があり、第二奨学金に比べ厳しい基準が設定されています。 また進学前に高校で申込む予約採用と、大学などの進学先で奨学金の申請をする在学採用では基準が異なります。予約採用で不採用でも在学採用で採用される可能性がありますので再チャレンジするとよいでしょう。
では、予約採用を中心に学力基準と家計基準をみてみましょう。

学力基準
高校生で申し込む予約採用では、「高等学校等における申込時までの全履修科目の評定平均値が、5段階評価で3.5以上であること」が必要です。 ただし、生計維持者(原則父母)の住民税(市区町村民税所得割)が非課税であるなど一定の場合、大学等へ進学後も優れた成績を修める見込みがある等として学校から推薦されれば、学力基準を満たすものとして扱われます。 在学採用の場合、1年生の学力基準は「高等学校又は専修学校高等課程最終2か年の成績の平均が、大学・短期大学では3.5以上、専門学校では3.2以上」を満たすことが必要です。2年生以上は「本人の属する学部(科)の上位1/3以内であること」となっています。 なお、予約採用同様、生計維持者(原則父母)の住民税(市区町村民税所得割)が非課税であるなど一定の場合、学力基準が緩和されています。
家計基準
予約採用では、生計維持者の年収(給与収入の場合)・所得金額(給与以外の収入の場合)等から特別控除額等を差し引いた金額(認定所得金額)が、世帯人数ごとに設定された収入基準額以下であることが必要です。 たとえば、収入額・所得の上限額の目安は、本人、親①(収入あり)、親②(無収入)、中学生4人世帯では、給与所得者の世帯では747万円程度、給与所得以外の世帯では349万円程度です。 なお、第二種奨学金では、それぞれ1,100万円程度、692万円程度、第一種奨学金と第二種奨学金の両方から貸与を受ける併用貸与の場合は、それぞれ686万円程度、306万円程度となります。
在学採用では、学種(大学・短大・専門学校)、設置者(国公立・私立)、世帯人数、通学形態(自宅通学・自宅外通学)により、収入額・所得の上限額の目安が細かく設定されています。たとえば、4人世帯で自宅から大学に通学する場合、収入額・所得の上限額の目安は、給与所得者の世帯では805万円程度、給与所得以外の世帯では397万円程度と予約採用より緩やかな基準となっています。
以前は採用枠(採用人数の制限)がありましたので選考基準(家計基準、学力基準)を満たしても採用されないことがありましたが、現在は選考基準を満たせば全員採用されます。
申込方法
申込方法は、進学する前に申し込む「予約採用」と進学した後に申し込む「在学採用」の二つがあります。
予約採用と在学採用の違いは以下のようになっています。
 出典:日本学生支援機構のホームページ
出典:日本学生支援機構のホームページ
予約採用で申し込む場合
高校の奨学金の説明会には必ず参加しましょう。高校から必要書類を受け取り提出期限内にインターネットで手続きをします。2浪までは在籍していた高校で申込むことができます。申込時点で進学先が決まっていなくても構いません。 申込時に「奨学金の種類・金額」、「利率の算定方式」、「保証制度」などをきめなければなりませんが、進学時に変更できます。また、奨学金の辞退もできますので、奨学金を利用する可能性があれば予約申込みをするとよいでしょう。 申込時期は限定されていますのでタイミングを逃さないようにしましょう。春募集(4月下旬~7月下旬)と秋募集(10月)があります。申込期間は各学校により異なりますので確認してください。なお、春募集で申込みした生徒等は秋募集での申込みはできません。
在学採用で申し込む場合
大学等の奨学金の説明会には必ず参加しましょう。大学等から必要書類を受け取り提出期限内にインターネットで手続きをします。 申込時期は限定されていますのでタイミングを逃さないようにしましょう。春募集(4月上旬~6月下旬)と秋募集(9月~11月頃)があります。申込期間は各学校により異なりますので確認してください。
緊急採用、応急採用で申し込む場合
在学中、⽣計維持者の失職、破産、事故、病気、死亡等もしくは⽕災、⾵⽔害等の災害等により家計が急変し、緊急に奨学⾦が必要になった場合に、随時申込むことができる貸与型の奨学⾦です。ただし、家計急変の事由が発⽣してから12か⽉以内の⼈で、学⼒・家計基準を満たすことが必要です。緊急採⽤が第⼀種奨学⾦(無利⼦)、応急採⽤が第⼆種奨学⾦(有利⼦)にあたります。
緊急採用の学力基準は、大学等における学業成績が、平均水準以上である者などと第一種奨学金に比べ緩やかです。 貸与⽉額は、緊急採⽤であれば第⼀種奨学⾦、応急採⽤であれば第⼆種奨学⾦と同じです。申込み及び学校からの推薦後、最短で翌⽉に奨学金が⼝座に振り込まれます。
詳しい申し込み方法や、申し込み書類の書き方はこちら「【奨学金申し込み書類の書き方解説】用意するものや申請理由の書く時に役立つ7つの例文を紹介!」で解説しているのでご確認ください。
返還に関して知っておくべきこと
貸与型の奨学金は将来返済する必要があります。近年は奨学金を返済できない人が増加していることが問題となっています。日本学生支援機構の調査によると、令和2年度の調査では3か月以上滞納している人が約3%います。
延滞している理由は、「本人の低所得」が62.9%で最も高く、次いで「奨学金の延滞額の増加」が41.4%となっています。男女別でみると、男性は女性に比べて「本人の借入金の返済」の比率が高く、女性は男性に比べて「本人の配偶者の経済困難」の比率が高い、結果となっています。
3か月以上滞納してしまうと金融事故として金融機関の注意者リストに載ってしまい、クレジットカードやローンの利用が制限されます。借りる前に返還額を確認し、借りすぎに注意しましょう。
また、返還は安定した職業に就くことが前提なので進学先の就職状況もよく調べましょう。
また、より詳しい返還方法に関しては奨学金の返済の仕方を解説|返済方法にはどんな種類があるの?で解説していますので、参考にしてください。
2種類の返還方法
 第一種奨学金のみ「所得連動返還方式」か「定額返還方式」のいずれかの返還方式を選択することができます。第二種奨学金は定額返還方式で固定されます。
第一種奨学金のみ「所得連動返還方式」か「定額返還方式」のいずれかの返還方式を選択することができます。第二種奨学金は定額返還方式で固定されます。
所得連動返還方式は所得に応じて毎月の返還額を毎年見直します。所得が低くなってしまった場合でも無理せず返還することができます。保証制度は機関保証が必須です。 所得連動返還方式を選択した方の返還初年度(返還開始から1年以内の最初の9月)の返還月額は、定額返還方式により算出された返還月額の半額と定められています。この金額での返還が困難な場合は、申請により2,000円(最低返還月額)での返還が可能です。
定額返還方式は文字通り、毎月定額を返済していく方法です。返還の計画が立てやすいなどのメリットがあります。 5万円を4年間(240万円)借りた場合、定額返還方式では返還額は月額約 13,333円(15年間)になります。 一方、所得連動返還方式では、年収300万円の方は月額約 8,600円、年収450万円の方は月額約 15,400円と 所得に応じて月々の返還額が決まります。
まとめ
以上、第一種奨学金の詳細な解説をさせていただきました。まず、進学にかかる費用を調べ、家計から支出できる金額を見積もり、不足分を算出して、教育ローン、奨学金、アルバイトなど、どの方法で補うのか家族で話し合いましょう。なお、初年度納付金など入学前に必要な費用は奨学金では補えないので注意しましょう。また、アルバイトは学業がおろそかにならない程度にとどめましょう。
奨学金は高等教育の修学支援新制度である給付型奨学金、貸与奨学金の順に検討します。貸与奨学金は無利子の第一種奨学金、有利子の第二種奨学金の順に検討します。 第一種奨学金は第二種奨学金に比べ貸与月額が少なく、さらに最高月額は家計基準が最も厳しい併用貸与の基準を満たさなければ選択できません。併用貸与の選考基準を満たさない場合は第一種奨学金にこだわらず第二種奨学金を選択するとよいでしょう。 また、給付型奨学金と併用する場合、第一種奨学金の貸与月額が調整(制限)されますので注意してください。
ガクシーでは、貸与型の奨学金だけでなく、返済の必要がない給付型の奨学金も数多く掲載しています。ガクシーに登録をすると、新着の奨学金をお知らせしたり、簡単に奨学金に応募することができます。この機会にぜひご登録ください。
▼会員登録する
https://gaxi.jp/auth/login
会員登録でもっと奨学金を活用しよう
ガクシーに会員登録すると、あなたにピッタリの奨学金情報や便利な機能が使えるようになります。無料で簡単に登録できます!
会員登録のメリット
- 奨学金リマインダーで、オトクな奨学金を見逃さない
- ガクシー上で奨学金に申込みができる
- プロフィール登録で、奨学金に申込み時の入力が簡単になる
- プロフィールに応じたオススメ奨学金情報がメールで届く

