【第二種奨学金】有利子の奨学金を借りるには?申し込み方法・採用基準・第一種との違いも解説!

 奨学金制度はもともと進学を考えているが経済的な理由で進学を断念しないようにという目的で設立された制度です。現在では奨学金を利用する学生は増えてきており、日本学生支援機構の調査によると2020年度の奨学金受給率は49.6%と約半数の学生が奨学金を利用しています。
奨学金制度はもともと進学を考えているが経済的な理由で進学を断念しないようにという目的で設立された制度です。現在では奨学金を利用する学生は増えてきており、日本学生支援機構の調査によると2020年度の奨学金受給率は49.6%と約半数の学生が奨学金を利用しています。
奨学金は大学が独自に行っているものや、企業、地方自治体などさまざまな団体が制度を設けております。日本学生支援機構(JASSO)が運営する奨学金は大学生の約3人に1人が利用しています。その中で第二種奨学金は比較的容易に借りれるため、特に利用者が多くなっています。
目次
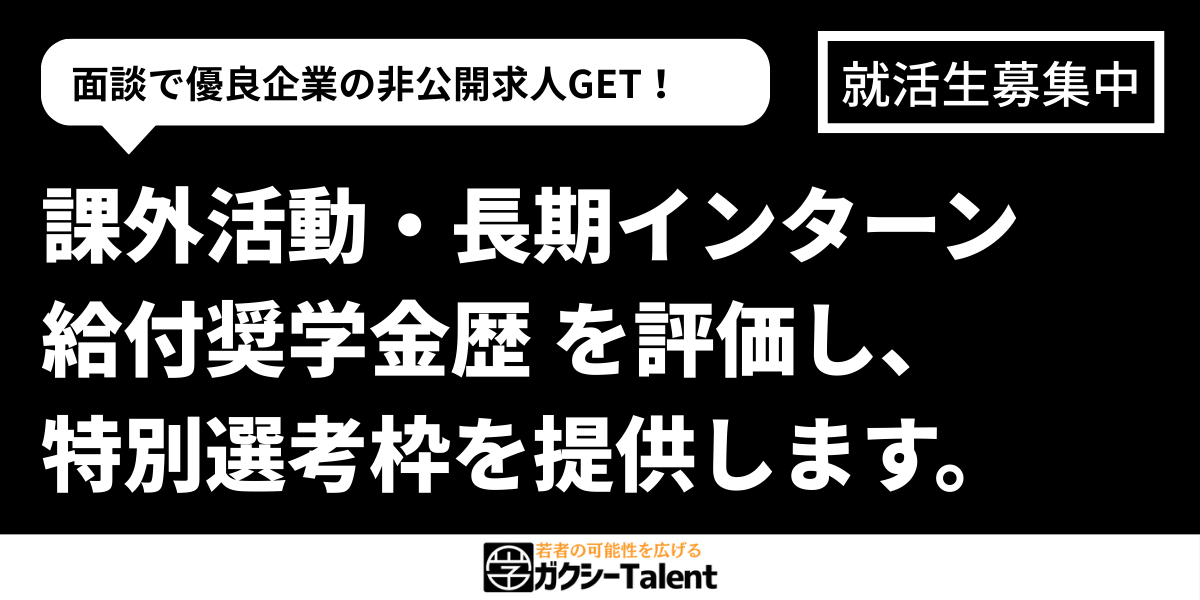
【就活生必見】ガクシーが独自評価で非公開求人をご提供。
ガクシーTalentは、課外活動・長期インターン・給付奨学金の選考歴を独自評価し、優良企業の非公開求人や特別選考枠を提供する就活サービスです
詳細を見る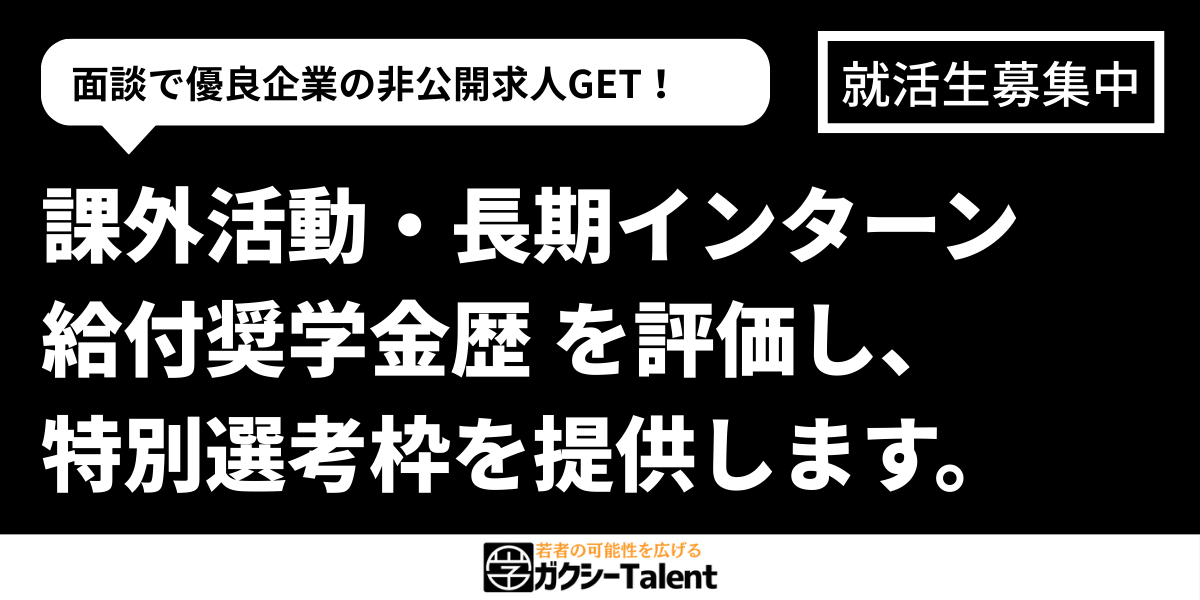
【就活生必見】ガクシーが独自評価で非公開求人をご提供。
ガクシーTalentは、課外活動・長期インターン・給付奨学金の選考歴を独自評価し、優良企業の非公開求人や特別選考枠を提供する就活サービスです
詳細を見る日本学生支援機構(JASSO)とは
日本学生支援機構は2004年に設立された独立行政法人で、それまで国の奨学金制度を運営していた日本育英会から事業を引き継いで現在制度を運営しています。学生支援事業を実施する文科省管轄の独立行政法人なので、日本学生支援機構が実施する奨学金制度は公的な国の支援制度です。
給付型奨学金と貸与型奨学金
 日本学生支援機構の奨学金には種類があります。返還の必要がない給付型と卒業後返還が必要になる貸与型です。貸与型の中でも無利子で借りることができる第一種奨学金と金利がかかってくる第二種奨学金が存在しています。
日本学生支援機構の奨学金には種類があります。返還の必要がない給付型と卒業後返還が必要になる貸与型です。貸与型の中でも無利子で借りることができる第一種奨学金と金利がかかってくる第二種奨学金が存在しています。
給付型奨学金
経済的理由で大学・専門学校への進学をあきらめないよう、2020年4月から修学支援新制度がスタートしました。このJASSOの修学支援新制度の中に給付型奨学金があります。修学支援新制度は返還を要しない給付型奨学金と授業料・入学金の免除または減額により、大学・短期大学、高等専門学校、専門学校を無償化する制度です。 採用されるには、家計基準(収入要件・資産要件)と学力要件の両方を満たす必要があります。しかし、世帯人数や家計基準、特定の学部などの条件を満たせば、学校の成績だけではなく、レポートや面談を通じてしっかりとした「学ぶ意欲」があれば支援を受けることができます。給付型奨学金の対象となれば、大学や専門学校の入学金や授業料も免除や減額されます。 またJASSOの給付型奨学金以外にも財団や自治体が行っている給付型奨学金もあります。
貸与型奨学金
貸与型奨学金には、利子がつかない第一種奨学金と利子がつく第二種奨学金があります。第一種奨学金は特に優れた学生や生徒を対象としており採用基準が厳しく設定されていますが、第二種奨学金は比較的ゆるやかな採用基準が設けられています。

第一種奨学金
採用基準には家計基準と学力基準があり、両方の基準を満たす必要があります。
高校で申込む予約採用の場合、学力基準は、「高等学校等における申込時までの全履修科目の評定平均値が、5段階評価で3.5以上であること」となっています。
家計基準は、生計維持者(父母)の年収(給与収入の場合)・所得金額(給与以外の収入の場合)等から特別控除額等を差し引いた金額(認定所得金額)が、世帯人数ごとに設定された収入基準額以下であること、となっています。
貸与月額は学校の設置者(国公立・私立)及び通学形態(自宅通学・自宅外通学)等により決まります。
詳しくはこちら「【無利子の奨学金】第一種奨学金を借りるには?申し込み方法・採用基準を徹底解説!」をご覧ください。
第二種奨学金
こちらは第一種とは違い、返還の際には利子をつけて返還する必要がある奨学金です。利率の上限は3%と定めれていますが、実際の利率は貸与終了時等の経済状況によって変化します。
過去5年間(3月)の利率は利率固定方式が0.070%~0.905%、利率見直し方式が0,002%~0.300%と教育ローンに比べ極めて低利で推移しています。
第二種奨学金の貸与月額
2万円~12万の中から希望する金額を1万円刻みで自由に選択することができます。12万円を選択した場合、授業料が高い傾向にある私立大学の獣医学部や薬学部へ進学する人はさらに2万円、医学部、歯学部へ進学する人はさらに4万円増額できます。
第一種奨学金との併用も可能なので、第一種奨学金の利用ができる人でも第一種の金額だけでは足らないと考えている人は併用も視野に入れて計画を立てることがよいでしょう。
ただし、併用するには第一種奨学金よりも厳しい家計基準をクリアすることが必要です。
第二種奨学金の学力基準
 こちらは第一種奨学金と大きく異なっています。学力基準として以下四つのうちいずれかに該当する人となっています。
こちらは第一種奨学金と大きく異なっています。学力基準として以下四つのうちいずれかに該当する人となっています。
- 出身学校または在籍する学校における成績が平均水準以上と認められる者
- 特定の分野で特に優れた資質能力を有すると認められる者
- 進学先の学校における学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見込みがあると認められる者
- 高等学校卒業程度認定試験合格者で、上記のいずれかに準ずると認められている者
引用:https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/taiyo_2shu/gakuryoku/zaigaku.html
こちら四つのうちいずれか一つに該当することができれば第二種奨学金の学力基準を満たします。ポイントは三つ目の条件です。
大学に進んで勉強をしようと思うからこそ奨学金を借りるので、進学を考えている人は三つ目の条件を満たしています。
また家計基準も第一種奨学金より緩く設定されており、2023年度の予約採用を例にみる本人、親①(収入あり)、親②(無収入)、中学生の4人世帯の収入・所得の上限額の目安は、給与所得者1,100万円程度、給与所得者以外692万円程度となっています。
以下に予約採用の場合の第一種奨学金と第二種奨学金の学力基準の違いをわかりやすく表にまとめたのでご覧ください。
| 学力基準比較 | 第一種奨学金 | 第二種奨学金 |
| 条件① | 高等学校等における申込時までの全履修科目の評定平均値が、5段階評価で3.5以上であること。(※) | 出身学校または在籍する学校における成績が平均水準以上と認められること。 |
| 条件② | なし | 特定の分野で特に優れた資質能力を有すると認められること。 |
| 条件③ | なし | 学修に意欲があり学業を確実に修了できる見込みがあると認められること。 |
| 条件④ | 高等学校卒業認定試験合格者であること。 | 高等学校卒業程度認定試験合格者で、上記のいずれかに準ずると認められること。 |
| 備考 | ①と④のいずれか満たしていれば可 | ①~④のいずれかを満たしていれば可 |
(※)上記の基準を満たさない場合であっても、生計維持者(原則父母)の住民税が非課税である者などは大学等へ進学後も優れた成績を修める見込みがある等として学校から推薦されれば、学力基準を満たすものとして扱われます。
利率の算定方法
第二種奨学金の利率は前述した通り上限が3%ですが、貸与終了時の経済状況によって利率の増減があります。利率の算定方法は「利率固定方式」と「利率見直し方式」があり、選択することができます。なお、奨学金貸与中、在学猶予中及び返還期限猶予中は利息はかかりません。無利子です。

利率固定方式
奨学金の貸与が終わった時に決定する利率が、返還完了まで適用され続ける算定方法になります。
利率見直し方式
返還期間中に約5年ごとに利率が見直される算定方法です。経済市場の金利が上昇すれば利率が高くなり、金利が下がれば利率は低くなります。
日本学生支援機構ホームページ「平成19年4月以降に奨学生に採用された方の利率」 から、それぞれの方式で算定した場合の利率を年度ごとに確認できます。
入学時特別増額
第一種・第二種奨学金では入学時特別増額を行うことができます。金額は10万円~50万円の範囲で10万円刻みで増額をすることができます。貸与できるのは一度だけです。しかし入学前に借りることはできないためこちらで増額を行っても、入学金に充てることはできないので注意してください。
ただし、入学時特別増額貸与奨学金の採用候補者となった人は、希望により、労働金庫(ろうきん)の「入学時必要資金融資」(つなぎ融資)制度に申し込むことができます。
入学時特別増額貸与奨学金を受けた場合、増額貸与利率は原則として基本月額に係る利率に0.2%上乗せした利率となります。また、この奨学金単独での申込みはできません。
申込み方法
日本学生支援機構の奨学金の申込方法は下記の通り三つあります。
- 予約採用の場合(入学前に申込み)
高校生3年次に申込みを行う方法です。
春募集(4月下旬~7月下旬)と秋募集(10月)があります。ただし、春募集で申込みをした生徒は秋募集での申込はみはできません。申込期間は高校等で異なりますので確認してください。
学校から申込み書類を受け取り学校が定める提出期限までに必要書類を学校に提出し、インターネットで申込みます。
採用候補者決定通知発行は10月~1月に行われます。進学後「進学届」を提出して正式に奨学生となります。
進学先が決まっていなくても申込みができ、キャンセルも行うことができますので、奨学金を利用する可能性があれば予約申込みをすることをお勧めします。
- 在学採用の場合(進学後に申込み)
進学してから奨学金の申込を行う方法です。
春募集(4月上旬~6月下旬)と秋募集(9月~11月頃)があります。申込期間は大学等で異なりますので確認してください。学校から申込み書類を受け取り学校が定める提出期限までに必要書類を学校に提出し、インターネットで申込みます。
予約採用で不採用になった場合でも、再度、進学後申込みを行うことができます。
- 緊急採用・応急採用の場合
⽣計維持者の失職、破産、事故、病気、死亡等もしくは⽕災、⾵⽔害等の災害等により家計が急変し、緊急に奨学⾦の必要が⽣じた場合に、随時申込むことができる貸与型の奨学⾦です。緊急採⽤が第⼀種奨学⾦(無利⼦)、応急採⽤が第⼆種奨学⾦(有利⼦)にあたります。
より詳しい申込書の書き方はこちら「【奨学金申し込み書類の書き方解説】用意するものや申請理由の書く時に役立つ7つの例文を紹介!」を参考にしてください。
返還方法と返還ケース
奨学金の返還は、貸与が終わった月の翌月から数えて7ヶ月目から始まります。返還方法には月賦返還と月賦・半年賦併用返還の二種類あります。割賦方法は返還誓約書で選択しています。返還誓約書で決めた割賦方法は原則変更できません。
月賦返還
割賦金が返還回数に応じて毎月引き落とされる返還方法です。毎月定額で引き落としがあり毎月27日に引き落とされます。
月賦・半年賦併用返還
返還する合計金額の半分は毎月返済し、もう半分は半年ごとに返済する方法です。1月と7月のみ月賦と半年賦をあわせて返済するため、その月は引き落としの金額が多くなります。
返還シミュレーション
まとめ
以上が第二種奨学金の解説になります。第二種奨学金は比較的簡単に借りることができますが、あくまで借金ということには注意しておく必要があります。第一種奨学金と違いこちらは利子がかかってきます。
奨学金制度は返還期間も非常に長いのでその分利子を支払い続ける必要があります。お金に余裕ができたら繰上げ返還をしましょう。返還期間が短くなる、利子を軽減できるといったメリットがあります。
自分の進路にはどれほど費用が必要なのか借りる前から計画を立てておくことが重要です。
また返還が難しい場合には日本学生支援機構に問い合わせて、承認を得られれば減額返還や返還期限猶予といった対応もとることができるので困った場合には必ず申請をするようにしましょう。これら救済措置は郵送による提出の方法に加え、スカラネット・パーソナルからでも提出できます。
奨学金が返還できなくなったときのより詳しい対処法はこちら「奨学金を返さないリスクって何がある?滞納した場合の対応方法も併せて解説!」にまとめてありますので、参考にしてください。
ガクシーでは、貸与型の奨学金だけでなく、返済の必要がない給付型の奨学金も数多く掲載しています。ガクシーに登録をすると、新着の奨学金をお知らせしたり、簡単に奨学金に応募することができます。この機会にぜひご登録ください。
▼会員登録する
https://gaxi.jp/auth/login
会員登録でもっと奨学金を活用しよう
ガクシーに会員登録すると、あなたにピッタリの奨学金情報や便利な機能が使えるようになります。無料で簡単に登録できます!
会員登録のメリット
- 奨学金リマインダーで、オトクな奨学金を見逃さない
- ガクシー上で奨学金に申込みができる
- プロフィール登録で、奨学金に申込み時の入力が簡単になる
- プロフィールに応じたオススメ奨学金情報がメールで届く


