【奨学金の新制度】2020年からリニューアルされた日本学生支援機構の「給付型奨学金」とは?

国内で最も多くの大学生が申し込みをしている日本学生支援機構(JASSO)の奨学金にはさまざまな種類のものがあります。 そのうちの一つである、2017年度から開始された奨学金制度「給付型奨学金」が2020年4月から新しくなり、より便利な制度となりました。
たとえば、従来の「給付型奨学金」制度に、進学した大学等での「給付型奨学金の増額」「入学金や授業料の減額・免除」が追加されました。 給付型奨学金の対象者は、制度対象の進学先に申し込めば、授業料などの減免の支援対象者となるのです。また2025年にも「理工農系・多子世帯」への支援拡充が追加されました。
本記事では、日本学生支援機構の給付型奨学金がどのように変わったか?をくわしく解説するとともに、その申し込み方法や、新制度の注意点もあわせて紹介します。
また、ガクシーでは充実した奨学金検索機能や、アカウント登録後のリマインド機能から、あなたに合った奨学金を見つけ忘れずに申し込みをするところまでサポートしています。
申し込みの期日のリマインドや、お得な奨学金情報は会員登録をすると受け取ることができます。 ぜひ登録してお得な奨学金情報をもらさずチェックしてください!
▼会員登録する
https://gaxi.jp/auth/login
目次
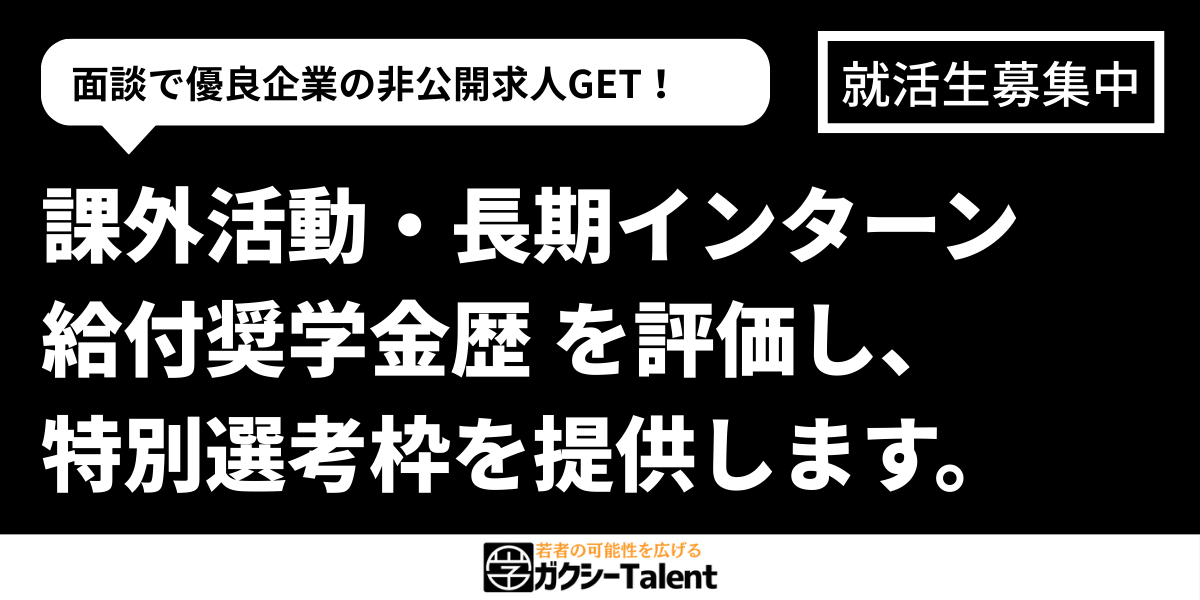
【就活生必見】ガクシーが独自評価で非公開求人をご提供。
ガクシーTalentは、課外活動・長期インターン・給付奨学金の選考歴を独自評価し、優良企業の非公開求人や特別選考枠を提供する就活サービスです
詳細を見る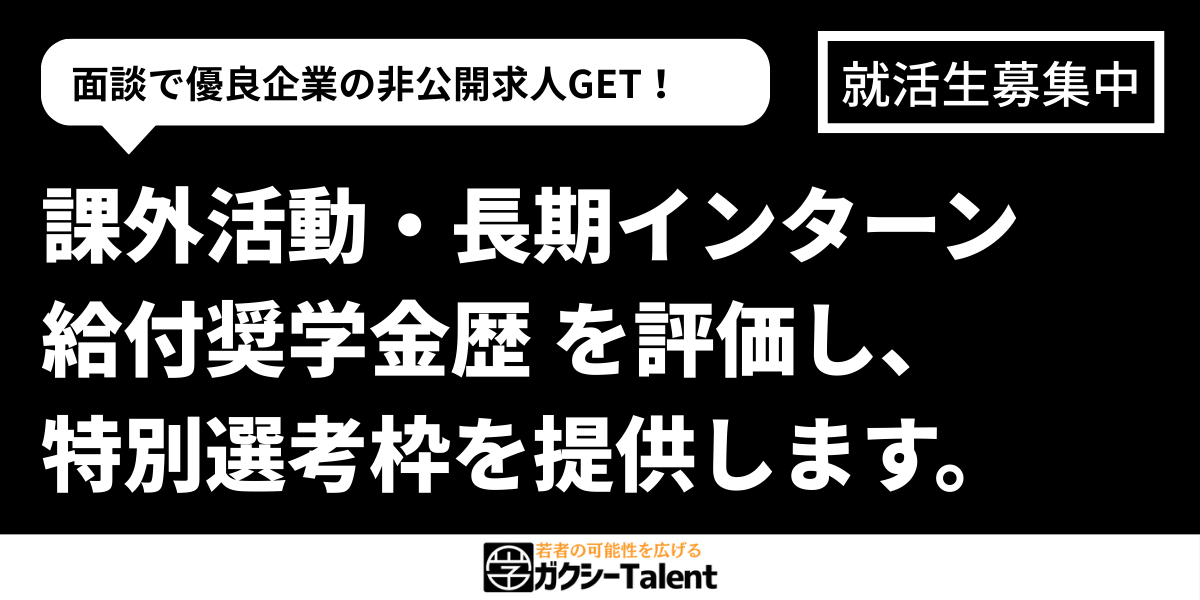
【就活生必見】ガクシーが独自評価で非公開求人をご提供。
ガクシーTalentは、課外活動・長期インターン・給付奨学金の選考歴を独自評価し、優良企業の非公開求人や特別選考枠を提供する就活サービスです
詳細を見る従来の奨学金制度とのちがい
従来の制度とのちがいは、大きく分けて「対象学生の増枠」「支給金額のアップ」「入学金や授業料免除・減額」の3点があります。

ちがいその①:対象学生の増枠

従来の給付型奨学金制度では、住民税非課税世帯の学生のうち、さらに学習成績が優秀な学生が選考される制度でした。各高校等において日本学生支援機構が示すガイドラインを参考とし推薦基準を定め、各高校等の推薦基準に基づき、生徒の学習状況に加え、進学の意欲・目的なども含めて総合的に判断し、給付奨学生を推薦しました。ガイドラインでは、以下のいずれかの要件を満たす者から推薦することとされていました。
- 十分に満足できる高い学習成績を収めている
- 教科以外の学校活動等で大変優れた成果、教科の学習で概ね満足できる成績を収めている
- 社会的養護を必要とする生徒等で、進学後の学修に意欲があり、進学後特に優れた学習成績を収める見込みがある
旧制度に対して新制度では予約採用の場合、「住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯」と「評定平均値が5段階評価で3.5以上」または「学ぶ意欲のある学生」が対象となっております。
「学ぶ意欲のある学生」については学校などにおける学修意欲が面談やレポートの提出で評価され、意欲が確認できれば選考の対象となり、成績が原因で奨学金の対象外になることがなくなりました。
「住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯」について、従来は収入が一定以下(住民税非課税世帯)のみの対象でしたが、令和7年度に法改正した後の新制度では世帯収入や学部、お子さまの人数に応じた4段階の基準で支援額が決まります。
区分に関しては下記の通りです。
| 所得の区分 (年収目安) | 支援区分 (1子・2子世帯) | 支援区分 (多子世帯) |
|---|---|---|
| ~270万円 | 第Ⅰ区分 | 第Ⅰ区分 (多子世帯) |
| ~300万円 | 第Ⅱ区分 | 第Ⅱ区分 (多子世帯) |
| ~380万円 | 第Ⅲ区分 | 第Ⅲ区分 (多子世帯) |
| ~600万円 | 第Ⅳ区分 (理工農系) | 第Ⅳ区分 (多子世帯) |
| 600万円~ | 不採用/停止 | 多子世帯 |
※実際の審査対象は「収入」ではなく住民税情報により算出された「支給額算定基準額」となります。
| 支援区分 | 収入基準(※1) |
|---|---|
| 第Ⅰ区分 | あなたと生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること(※2) 具体的には、あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円未満であること |
| 第Ⅱ区分 | あなたと生計維持者の支給額算定基準額(※3)の合計が100円以上25,600円未満であること |
| 第Ⅲ区分 | あなたと生計維持者の支給額算定基準額(※3)の合計が25,600円以上51,300円未満であること |
| 第Ⅳ区分 | あなたと生計維持者の支給額算定基準額(※3)の合計が51,300円以上154,500円未満であること |
※1収入については、2023年(1月~12月)の収入に基づく2024年度住民税情報により算出された支給額算定基準額が上表に該当するか審査を行います。申込後に減収(失業等)があっても状況を鑑みることはできません(申込時の収入等に変更が生じていても審査には考慮しません)。
※2ふるさと納税、住宅ローン等の税額控除等(臨時的な減税措置を含む。)は収入基準判定に影響しません。
※3支給額算定基準額(a)=課税標準額×6%-(市町村民税調整控除額+市町村民税調整額)(b)(100円未満切り捨て)
支給額算定基準額を算出するための「課税標準額」「市町村民税調整控除額」「市町村民税調整額」は、課税証明書や所得証明書に必ず記載されているものではありません。なお、「マイナポータル」を活用すれば、市町村民税の課税標準額などを調べることができます。
従来の給付型奨学金では「住民税非課税世帯」しか奨学金を受給できませんでしたが、新制度では対象が広がり、「それに準ずる世帯」も対象と成り、住民税非課税世帯の3分の2(第Ⅱ区分)の支援または3分の1(第Ⅲ区分)の支援を受けられるようになりました。
さらに、旧制度では、高校等ごとの推薦枠(人数上限)がありましたが、新制度では推薦枠はなくなりました。
自分が対象者であるかどうかを知るためには、本人と生計維持者(父母)の住民税情報を把握する必要があるので、市区町村民税を納税している自治体で発行される課税証明書やマイナポータルで確認しましょう。
ちがいその②:支給金額のアップ
新制度では支給額が増額されました。 住民税非課税世帯で私立大学(自宅通学)の学生の場合、それまでの支給額は月3万円でしたが、新制度では月3万8300円、年額約46万円に増額されました。
とくに生活費がより多くかかると想定される私立大学に通う自宅外生への支援額を、一年あたりの金額に変換すると、旧制度では国公立は36万円、私立は48万円でしたが新制度では国公立は約80万円、私立は約91万円と大幅に増加しました。
さらに世帯の収入に応じて以下のように4区分に分けられ、この区分に基づいて給付額(月額)が変わります。
国公立の場合
| 区分 | 自宅通学 | 自宅外通学 |
|---|---|---|
| 大学・短期大学・専修学校(専門課程) | ||
| 第Ⅰ区分 | 29,200円(33,300円) | 66,700円 |
| 第Ⅱ区分 | 19,500円(22,200円) | 44,500円 |
| 第Ⅲ区分 | 9,800円(11,100円) | 22,300円 |
| 第Ⅳ区分(多子世帯に限る) | 7,300円(8,400円) | 16,700円 |
| 高等専門学校(第4学年以上) | ||
| 第Ⅰ区分 | 17,500円(25,800円) | 34,200円 |
| 第Ⅱ区分 | 11,700円(17,200円) | 22,800円 |
| 第Ⅲ区分 | 5,900円(8,600円) | 11,400円 |
| 第Ⅳ区分(多子世帯に限る) | 4,400円(6,500円) | 8,600円 |
私立の場合
| 区分 | 自宅通学 | 自宅外通学 |
|---|---|---|
| 大学・短期大学・専修学校(専門課程) | ||
| 第Ⅰ区分 | 38,300円(42,500円) | 75,800円 |
| 第Ⅱ区分 | 25,600円(28,400円) | 50,600円 |
| 第Ⅲ区分 | 12,800円(14,200円) | 25,300円 |
| 第Ⅳ区分(多子世帯に限る) | 9,600円(10,700円) | 19,000円 |
| 高等専門学校(第4学年以上) | ||
| 第Ⅰ区分 | 26,700円(35,000円) | 43,300円 |
| 第Ⅱ区分 | 17,800円(23,400円) | 28,900円 |
| 第Ⅲ区分 | 8,900円(11,700円) | 14,500円 |
| 第Ⅳ区分(多子世帯に限る) | 6,700円(8,800円) | 10,900円 |

※本人(18歳)・父(給与所得者)・母(無収入)・中学生の4人世帯の場合
※第Ⅳ区分については、
・多子世帯の場合に給付型奨学金(支援上限額の1/4)及び授業料等減免(上限まで)
・私立学校理工農系学部等の場合に給付型奨学金の支給はありませんが、授業料等減免(支援上限額の1/3もしくは1/4)
の支援が受けられます。
出典: 日本学生支援機構のパンフレット
出典: 日本学生支援機構のHP
支給額については日本学生支援機構のホームページでシミュレーションできるので、確認するようにしましょう。
▼シミュレーションはこちらから
進学資金シミュレーター - JASSO
ちがいその③:入学金の減額又は免除
新制度で一番の変化は、給付型奨学金の支給にプラスして「入学金や授業料の減額・免除」が追加されたことです。ただし、入学金の免除・減額を受けられるのは、入学後3か月以内に申請して支援対象となった学生等ですので申請時期に気を付けましょう。
申し込み時期・手順
給付型奨学金を予約採用で申し込む場合は、高校3年の4月下旬~7月下旬に、学校から申込書類をもらいましょう。日本学生支援機構(JASSO)へスカラネット(インターネット)で申込み、学校に必要書類を提出します。また、マイナンバー(本人分・父母等分)をJASSOに直接、提出します。マイナンバーの提出期限はスカラネット申込完了後1週間以内と短期なので注意してください。
申込み期間は高校等により異なりますので確認してください。
授業料などの減免は、入学時に、進学先の大学等に申し込みます(入学金の免除・減額を受けられるのは、入学後3か月以内に申請して支援対象となった学生等ですので申請時期に気を付けましょう)。
対象者である場合は下記の手続きを行います。

また、これら手続きを行う際の注意点は次の通りです。
※マイナンバーは「学生本人だけでなく父母のもの(最大3人)」 が必要なため注意。
※身分確認書類は「学生本人のものだけ」 用意。
・1点の提出で認められるもの: マイナンバーカードの表面、 パスポート、 運転免許証、 顔写真付きの学生証、 顔写真付きの生徒手帳の身分証明書、 障害者手帳 など
・2点の提出が必要なもの: 健康保険証、 顔写真なしの学生証、 顔写真なしの生徒手帳の身分証明書、 在学証明書、 年金手帳、 住民票の写し など
予約申込後、採用候補者決定通知が高校を通じて交付されます。この段階ではまだ正式な奨学生ではありません。
進学後、進学先の奨学金担当窓口に採用候補者決定通知と必要書類を提出します。その後、インターネットで期限内に「進学届」を提出します。 「進学届」を提出しないと給付奨学生として採用されず、採用候補者としての権利を失いますので注意してください。なお、給付奨学金(新制度)の誓約書の提出は不要になりました。
申し込み書類の書き方に関してはこちら「【奨学金申し込み書類の書き方解説】用意するものや申請理由の書く時に役立つ7つの例文を紹介!」の記事で詳しく紹介しているので参考にしてみてください。
新制度の奨学金注意点
注意点その①:高校生の場合、奨学金が入学前に振り込まれない。
大学へ進学予定の高校生に給付型奨学金が初回入金されるのは、予約採用では進学後「進学届」等の必要書類が不備なく提出された場合、提出月からおおむね1~2か月後です。なお、在学採用では申込書類が不備なく提出された場合、申込締切月の2か月後です。いずれも初回振込時に、貸与開始月からの奨学金をまとめて振り込んでくれます。
私立大学の場合、合格後1~2週間以内に入学金や前期分の学費を納付するのが一般的です。
大学のルールによっては入学前の段階で入学金または、授業料が必要となる場合があるので事前に大学の窓口での確認が必要です。
入学前に入学金など必要な費用が用意できる場合は、安心です。 費用が用意できない場合、大学によっては入学金が払われないと入学を辞退したとみなされることもありますので、大学の窓口に延期できないか相談してみて下さい。延納できない場合に備えて教育ローンの申込みも合格発表前に余裕をもってしておきましょう。
注意点その②:大学院への進学時には新制度の奨学金は対象外となる。
日本学生支援機構の給付型奨学金は、大学院に進学する場合には利用することができません。 しかし、貸与型であれば申し込みが可能なため必要であれば利用しましょう。
また、民間の奨学金であれば大学院生を対象とした給付型奨学金も多く存在します。 例として電通育英会の奨学金を紹介しますので、興味があればこちら「【返済不要の奨学金】電通育英会の奨学金の内容・選考方法を徹底解説」の記事をごらんください。
注意点その③:学業成績により、支援の返還や打ち切りを求められる場合がある。
進学先での学業成績が良くないと、奨学金の返還や打ち切りを求められる場合があります。
奨学金が打ち切られる際は、まずはじめに大学から「警告」という処置通知が交付されます。その後「警告」の内容が改善されない場合に「停止」「廃止」の2つのパターンの処置があります。

給付奨学生として採用された後も、学習状況や生活状況に関する審査が毎年度末に1度(高等専門学校や短期大学、修業年限が2年以下の専門学校においては年2回)行われ、次年度も引き続き給付奨学金の受給が可能かどうかを審査します(「適格認定」といいます)。
審査の結果、適格認定(学業)の認定基準」に基づき「継続」、「警告」、「停止」、「廃止」に区分され処置されます。
- 「警告」
給付奨学金の支給を継続しますが、学業成績が向上せず、次回の適格認定時に再度「警告」の認定となった場合は、給付奨学金は「廃止」となります。 - 「停止」
3か月未満の停学又は訓告処分の場合、給付奨学金の支給を停止します。停学又は訓告処分終了後、学校からの報告を受けて給付奨学金の支給を再開します。 - 「廃止」
給付奨学金の支給を取り止めます(給付奨学生の資格を失います)。学校処分が退学、除籍、無期停学又は3か月以上の停学の場合、学業成績が著しく不良でやむを得ない事由がない場合は、併せて支給済みの給付奨学金の返還を求めます。
「警告」や「廃止」の認定を受けないよう、今一度以下の適格認定基準をご確認ください。
ではそれぞれの処置の基準を説明します。
まずは「警告」の通知が来る基準です。
・修得単位数の合計数が標準単位数の6割以下の場合
・GPA(平均成績)等が下位4分の1の場合
・出席率8割以下など、学修意欲が低いと学校が判断した場合
※ 「廃止」又は「警告」の基準に当てはまる場合であっても、災害、傷病その他のやむを得ない事由がある場合等には、「廃止」又は「警告」とならない場合があります。
基本的に学業不振、または学ぶ意欲の欠如が見られることが「警告」の条件になっていると言えます。そもそも奨学金は経済的に苦しむ、学ぶ意欲がある学生を支援するための制度となっているとめ、その対象から外れてしまうと支援を打ち切られる可能性が高くなります。
つぎに「停止」の場合を紹介します。
3か月未満の停学又は訓告処分の場合、給付奨学金の支給を停止します。停学又は訓告処分終了後、学校からの報告を受けて給付奨学金の支給を再開します。
「停止」は学費が発生しない状況になったときにとられる処置です。奨学金を受け取る資格がなくなったわけではないので、停学または訓告処分終了後に学校から日本学生支援機構に報告をしてもらうように後押しするとよいでしょう。
最後に「廃止」の場合を紹介します。
以下のいずれかに該当する場合、「廃止」となります。
・修業年限で卒業できないこと(卒業延期)が確定した場合
・修得単位数の合計数が標準単位数の5割以下の場合
・出席率が5割以下など、学修意欲が著しく低いと学校が判断した場合
・連続して「警告」に該当した場合
警告とおなじく、「廃止」も学業に前向きでない方が対象となるようです。
また、下記のケースに該当すると奨学金の廃止だけではなく授業料等の返還が命じられることもありますので、注意が必要です。
- 偽りその他不正の手段により支援措置を受けた場合
- 大学等から退学・停学(無期限又は3カ月以上)の懲戒処分を受けた場合
- 学業成績が著しく不良(累積取得単位数が標準単位数の1割以下)であり、災害、傷病その他のやむを得ない事由がない場合
以上が適格認定(学業)の注意点です。もらえると思っていた奨学金がもらえなかったり、奨学金が打ち切られたりすることがないよう、注意点を押さえて奨学金を利用していきましょう。
なお、適格認定には適格認定(家計)もあります。奨学金支給期間中、毎年、奨学生本人及び生計維持者(父母等)の経済状況に応じた支援区分の見直しを行い、10月以降の1年間(家計急変事由が適用されている場合は、3か月ごと)の支援区分を決定します。
■学業の適格基準
| 廃止(返還が必要) | ・ 累積修得単位数が標準単位数の1割以下であるとき ・ 3か月以上の停学、または退学処分を受けたとき ・偽りその他不正の手段により支援措置を受けたとき |
| 廃止(返還が不要) | ・卒業延期が確定した場合 ・修得単位数の合計数が標準単位数の5割以下の場合 ・出席率が5割以下など、学修意欲が著しく低いと学校が判断した場合 ・「警告」を2年連続で受けたとき |
| 警告 | ・ 累積修得単位数が標準単位数の6割以下であるとき ・ 単年度GPAの学部回生別順位が下位1/4以下であるとき |
| 継続 | ・ 上記どれにも属さないとき |
※災害、傷病、その他、斟酌すべきやむを得ない(本人の責に帰さない)事由がある場合は、『廃止』または『警告』区分に該当しない」という特例措置があります。
注意点その④:家計基準について父母のほか、本人(学生)の収入・資産も対象
家計基準について父母のほか、本人(学生)の収入・資産も対象です。
申告時点における本人及び生計維持者(父母)の資産額の合計が、生計維持者が2人の場合は2,000万円未満、1人の場合は1,250万円未満であることが必要です。
資産とは、現金及びこれに準ずるもの(投資信託、投資用資産として保有する金・銀等)、預貯金(普通預金、定期預金等)、有価証券(株式、国債、社債、地方債等)、満期や解約により現金化した保険をいいます。
土地・建物等の不動産、満期・解約前の掛け金、及び貯蓄型生命保険や学資保険は対象になりません。現預金の多い方は貯蓄型生命保険などに組み替えるとよいでしょう。
また、収入基準・資産基準の審査対象には生計維持者(父母)だけではなく本人(生徒・学生)も入ります。アルバイトのし過ぎに注意しましょう。
注意点その⑤:第一種奨学金との併用には制限がある。
給付奨学金と併せて第一種奨学金の貸与を受ける場合、給付奨学金の支援区分等に応じて、第一種奨学金の貸与月額は調整されます。なお、第二種奨学金との併用は制限がありません。
注意点その⑥:大学等の要件がある。
国又は自治体による要件確認を受けた大学等が対象です。対象校でないと給付奨学金を受給できません。令和5年1月20日現在、大学・短期大学の97.8%、高等専門学校の100%、専門学校の77%が対象になっています。
給付奨学金の利用を希望している人は事前に進学先が対象校か確認してください。
注意点その⑦:第一種奨学金との併用には制限がある。
無利子の第一種奨学金と併用する場合、第一種奨学金の貸与月額が調整され、住民税非課税世帯の学生の場合、0円と言う場合もあります。なお、有利子の第二種奨学金との併用ではこのような制限はありません。
注意点⑧:大学等に進学するまでの期間
予約採用の場合は高校等を初めて卒業又は修了した年度の末日から、支援の申請する日までの期間が2年以内、在学採用の場合高校等を初めて卒業又は修了した年度の翌年度の末日から、確認大学等に入学した日までの期間が2年以内という制限がありますので注意しましょう。
たとえば、2023 年 3 月に高校を卒業した場合、2025 年度末までに進学した者は対象となりますが、2026 年 4 月以降に進学した者は対象外となります。
まとめ
ここまで、2020年より新制度として生まれ変わった日本学生支援機構の「給付型奨学金」の解説をしてきました。 従来の給付型奨学金に比べ、新制度の給付型奨学金は授業料・入学金の支援や、支給対象が増枠されたりなど、支援が拡大しました。 給付型と貸与型の奨学金を組み合わせることによって、最大限学生生活の負担を減らすこともできるので、進学する際は自分に合った奨学金のプランニングをすることをおススメします。
なお、内閣官房「教育未来創造会議 提言」によると、給付型奨学金の支給と授業料等の減免は現在、年収の目安が380万円未満の低所得層の学生を対象ですが、中間層の多子世帯や理工系、農学系の学生への対象拡大が2024年度実施に向けて検討されてます。
ガクシーでは充実した奨学金検索機能や、アカウント登録後のリマインド機能から、あなたに合った奨学金を見つけ忘れずに申し込みをするところまでサポートしています。
申し込みの期日のリマインドや、お得な奨学金情報は会員登録をすると受け取ることができます。 ぜひ登録してお得な奨学金情報をもらさずチェックしてください!
▼会員登録する
https://gaxi.jp/auth/login
会員登録でもっと奨学金を活用しよう
ガクシーに会員登録すると、あなたにピッタリの奨学金情報や便利な機能が使えるようになります。無料で簡単に登録できます!
会員登録のメリット
- 奨学金リマインダーで、オトクな奨学金を見逃さない
- ガクシー上で奨学金に申込みができる
- プロフィール登録で、奨学金に申込み時の入力が簡単になる
- プロフィールに応じたオススメ奨学金情報がメールで届く


